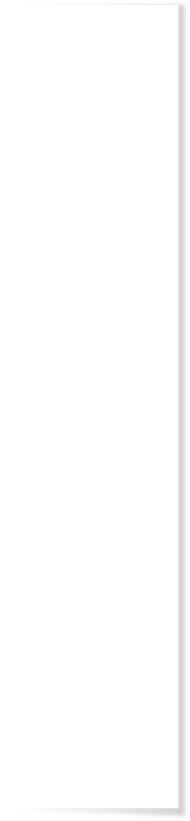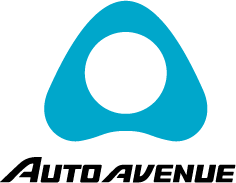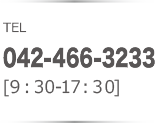2024年10月から本格化。OBD車検の全貌を徹底解説
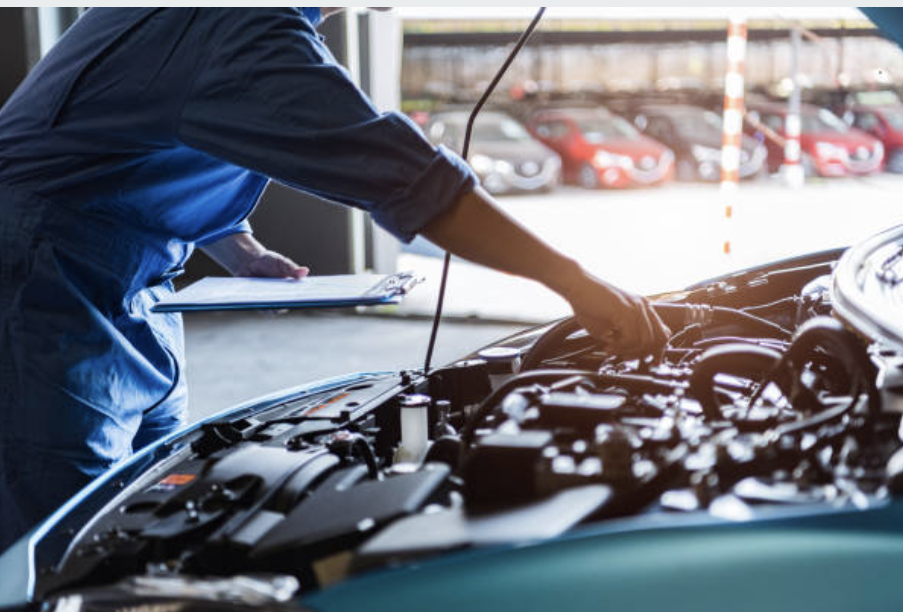
2024年10月から新たに導入される「OBD車検」は、自動車の安全性と環境性能をさらに向上させるために開発された最新の検査システムです。
従来の車検とは異なり、電子制御システムに基づいた自己診断機能(OBD)を活用して、車両のさまざまな不具合や潜在的な問題を早期に検出します。
本記事では、OBD車検の概要や導入の背景、具体的な検査内容、そしてドライバーが知っておくべき注意点について詳しく解説していきます。
新しい検査基準を理解し、安全で快適なカーライフを実現するために、OBD車検の重要性とメリットをぜひご確認ください。
車検は何年ごとに受けるべきなのか?車検に必要なものをまとめた記事はこちらです。
一度お読みいただければと思います。
関連記事:
車検は何年ごとに受けるべき?知っておきたい基礎知識とスケジュールの確認方法

目次
OBD車検とは?新たに導入される検査の目的と背景
OBD車検の導入背景と目的
OBD車検は、車両の安全性と環境保護の向上を目的として、新たに導入される検査システムです。特に、昨今の交通環境では、車両の不具合や故障が重大な事故や環境問題の原因となり得るため、安全性の確保と環境保全の観点からの対策が求められています。
近年の自動車技術は、エンジンやブレーキなどの基本的な構造から電子制御に基づくシステムへと急速に進化しています。この進化に伴い、車両の電子制御装置(ECU:Electronic Control Unit)が多くの機能を担い、車両全体の状態を管理しています。ECUの導入により、従来の機械的な故障だけでなく、電子的なトラブルが発生する可能性も増えてきました。
このような背景から、車両の自己診断機能であるOBD(オンボード・ダイアグノスティックス)を活用することで、不具合や故障を早期に発見し、ドライバーや整備士が迅速に対応できる環境を整える必要が生じました。OBD車検は、エンジンや排気システム、ブレーキなどの重要なコンポーネントの状態を診断し、適切な整備が行われているかどうかを確認することを目的としています。
このシステムの導入により、保安基準に違反している車両や環境基準に適合していない車両をより正確に特定できるようになり、安全で持続可能な交通環境の実現を目指します。OBD車検は、車両の不具合が交通安全や環境に及ぼす影響を最小限に抑え、運転者と社会全体にとって安心できる移動手段の確保を支える重要な役割を果たすのです。
OBD車検の仕組み
OBD車検は、車両に搭載されたOBDシステムを活用して、車両の内部状態を詳細に検査する新しい手法です。具体的には、エンジンや排気システム、電子機器の状態をチェックし、不具合が発生しているかどうかを診断します。このプロセスでは、車両のECUが重要な役割を果たしており、各種センサーからのデータを集めてシステム全体を監視します。
OBDシステムは、エンジンや排気システムに異常がある場合、エラーコード(DTC:Diagnostic Trouble Code)を自動的に生成します。DTCは、特定の異常を示すコードであり、例えば、排ガスシステムに問題がある場合やエンジン制御に異常がある場合などに、エラーコードとして表示されます。整備士は、このコードをもとに不具合の原因を特定し、必要な修理や調整を施すことができます。
従来の目視や手動による検査では発見が難しかった不具合も、OBD車検によって自動的に検出できるため、車両の安全性が大幅に向上します。特に、電子制御化が進む現代の車両において、OBD車検は、効率的かつ正確に問題を特定し、車両の安全と環境基準の維持に貢献する新しい検査手法として注目されています。
OBD車検の開始時期と今後の展望
OBD車検は、2024年10月から正式に施行される予定です。この施行により、日本国内で登録されている一部の車両がOBD車検の対象となり、これまで以上に厳密な安全基準が適用されることになります。OBD車検の普及により、車両の不具合や故障が早期に発見されるだけでなく、交通事故や環境への影響が低減することが期待されています。
今後、OBD車検が一般的な車検システムとして普及することで、車両の電子制御システムの健全性を確保し、ドライバーと社会全体にとって安全な移動手段が提供されることが期待されます。さらに、OBD車検の導入に伴い、整備工場やディーラーには高度な診断機器と技術が求められるため、整備業界全体の技術力向上にも寄与するでしょう。
また、将来的には、より精密で包括的な検査基準が追加される可能性もあります。例えば、電子制御化が進む中で、ハイブリッド車や電気自動車のシステム診断をも含むようなOBD車検の発展が予測されます。これにより、自動車業界全体の技術革新が促進されるとともに、ますます高度な安全・環境基準が確保されることが見込まれています。
2024年10月の施行を皮切りに、OBD車検は日本の交通社会における新たな基盤となり、車両の安全性向上と環境保護において重要な役割を担っていくでしょう。これにより、ドライバーが安心して運転できる環境が整備され、持続可能な未来の実現にも大きく貢献することが期待されています。
OBD車検の5つのメリット
メリット1:保安基準違反の早期発見
OBD車検を導入することにより、保安基準に違反している車両を迅速に検出することが可能になります。これは、交通安全を確保するうえで非常に重要なメリットです。
従来の検査方法では、目視や人の手による点検に頼ることが多く、特に電子制御に関わる細かな不具合は見逃されがちでした。しかし、OBD車検は車両の電子制御システムを活用して、エラーコードを通じて異常を自動的に検出します。これにより、点検の精度が飛躍的に向上し、重大な事故を未然に防ぐことが可能になります。
例えば、エンジンや排気システムの異常が早期に発見されることで、故障が大きな事故や環境汚染につながる前に対応が可能です。OBD車検は、このような潜在的なリスクを未然に察知し、安全な車両状態を維持するための強力なツールとなります。
メリット2:詳細な診断結果の通知
OBD車検を利用することで、従来よりもはるかに詳細な診断結果が得られます。これは、整備士が的確に修理や整備を行うための有益な情報を提供するものです。
具体的には、エンジンの各部位や排気システム、ブレーキなど、車両の多様な機能に関するデータが自動的に収集・分析されます。この診断結果に基づき、修理や部品交換が必要な箇所が明確に示されるため、正確なメンテナンスが可能となります。
このような詳細な診断結果により、車両の安全性を確保するだけでなく、環境保全にも寄与します。例えば、燃費の改善や排出ガスの削減といった効果も期待できるため、車両の総合的なパフォーマンス向上にもつながります。
メリット3:警告ランプの不具合検知
OBD車検のもう一つの利点は、警告ランプの異常点灯や消灯に関する問題を検知できる点です。多くのドライバーにとって、警告ランプは車両の状態を判断する重要な目安ですが、ランプの不具合によって本来通知されるべき異常が見逃されるリスクがあります。
OBDシステムを通じて、警告ランプの異常点灯や消灯が検出されると、整備士はすぐに原因を特定し、適切な対策を講じることができます。これにより、ドライバーが気づきにくい不具合も早期に発見され、迅速に対応することが可能です。
結果として、車両のトラブルを未然に防ぎ、安全な運転環境を維持するための大きな助けとなります。また、OBD車検は、警告ランプ自体の状態も診断するため、ドライバーにとって安心感を提供します。
メリット4:人為的なミスの防止
OBD車検のプロセスは、車両の状態を自動で診断するシステムに基づいているため、人為的なミスを最小限に抑えることができます。従来の点検方法では、点検者の経験や技量に依存する部分が大きく、ミスが発生するリスクがありました。
OBD車検では、診断機器が車両の状態を客観的にチェックするため、点検者による見落としや誤判断が発生しにくくなります。これにより、検査の信頼性が向上し、より正確な診断が実現します。
このような自動化された診断は、特に複雑な電子制御システムを備えた現代の車両において、その効果を発揮します。ドライバーにとっては安心感を提供すると同時に、整備士にとっても効率的な作業環境をサポートするメリットがあります。
メリット5:警告ランプ点灯なしでも不具合を特定
OBD車検の最大の特徴は、警告ランプが点灯していない場合でも、システムに潜在する異常を検知できることです。通常、ドライバーが異常に気づくのは、警告ランプが点灯してからですが、OBDシステムはそれ以前に潜在的な不具合を検出することが可能です。
これにより、警告ランプが点灯する前に適切な対応をとることができ、大きな故障やトラブルを未然に防ぐことができます。例えば、エンジン内部の小さな異常が将来の重大なトラブルにつながる前に発見され、適切なメンテナンスが実施されることで、車両の寿命が延びる可能性も高まります。
ドライバーにとっては、安全性が向上するだけでなく、突然のトラブルによる修理費用の増加を防ぐメリットもあります。OBD車検は、車両の健全性を長期間維持するために欠かせないシステムであり、今後の車両管理において重要な役割を果たすと考えられています。
車検を受けるのに最適な時期は、こちらの記事で知っていただければと思います。
関連記事:車検が受けられるのはいつから?最適な車検時期と注意点を徹底解説

OBD車検の対象車両と検査要件
OBD車検の対象車両
OBD車検の対象となる車両は、主に新型車や高度な電子制御システムを搭載した車両が中心となります。この選定は、近年の自動車が電子技術の進歩により、複雑なシステムによって制御されていることが背景にあります。特に、エンジンや排気システムにおいて電子管理が進んでおり、それに伴って車両の不具合も従来の機械的なトラブルから、電子制御に関わるものが増えてきました。
具体的には、OBD車検は、電子制御エンジンや電子式の排ガス処理システムなど、環境や安全性に直結する要素が搭載された車両を優先的に検査対象としています。これにより、環境保護と交通安全の両面において効果が期待されており、国の基準を満たした車両のみが安全な走行を保証されるようになります。
また、OBD車検の対象となる車両には、新たに開発される車両だけでなく、既存の車両であっても一定の基準を満たすものが含まれる予定です。これにより、より広範囲な車両に対して安全性が確保されるとともに、ユーザーにとっても安心して運転できる環境が整備されます。
OBD車検の対象装置
OBD車検では、特定の重要な装置が検査の対象として設定されています。これには、エンジン制御ユニット(ECU)、排気ガス処理装置、電子制御ブレーキシステムなどが含まれ、それぞれの装置が正常に機能しているかを確認することが求められます。
まず、エンジン制御ユニット(ECU)は、車両の電子制御システムの中心的な役割を果たしています。ECUはエンジンの燃料噴射や点火タイミングを管理し、燃費効率や排気ガスのクリーンさを維持するために重要な役割を担っています。ECUに異常があると、車両の性能低下や環境への負荷増加につながるため、OBD車検では厳密な検査が行われます。
次に、排気ガス処理装置は、車両から排出される有害物質を削減するための装置です。排ガスには、環境や人の健康に悪影響を及ぼす成分が含まれており、これを適切に処理することは非常に重要です。OBD車検では、排気ガス処理装置が適切に作動しているかどうかを確認し、環境への負荷を低減する取り組みをサポートします。
さらに、電子制御ブレーキシステムも重要な対象装置です。ブレーキは車両の安全性に直結する装置であり、電子制御化が進んでいる現代の車両では、このシステムが正常に機能していることが必須です。OBD車検においては、電子制御ブレーキシステムが異常なく作動しているかを確認し、ドライバーの安全を守るための重要な役割を果たします。
これらの対象装置を検査することで、OBD車検は車両の安全性と環境性能の両面を確保し、ドライバーや社会にとって信頼できる車両を提供するための取り組みを行っています。
OBD車検の検査費用について
OBD車検の費用は、従来の車検費用に比べて多少の追加料金がかかると予想されます。これは、OBD車検が従来の目視検査や基本的な機械的点検に加えて、電子制御システムをチェックする専用の診断機器や技術を必要とするためです。最新の技術を用いた検査は、より精密で詳細な結果が得られる一方で、その分のコストが増加します。
ただし、具体的な費用は車両の種類や検査内容によって異なるため、一概には言えません。例えば、エンジン制御ユニットや排気ガス処理装置、電子制御ブレーキシステムなどの状態が良好であれば、追加の整備が必要なく、費用も抑えられる可能性があります。しかし、これらの装置に異常が見つかった場合は、修理や部品交換が必要となり、費用が増加する可能性があります。
そのため、OBD車検を受ける際には、事前に整備工場やディーラーで詳細な見積もりを取得することが推奨されます。見積もりを確認することで、具体的な費用の内訳がわかり、予算計画を立てる上で役立つでしょう。ドライバーにとって、車両の安全性を確保するための重要な投資と考え、適切なメンテナンス費用を見込んでおくことが重要です。
OBD車検の具体的な手順と流れ
OBD車検の具体的な流れは、まず車両のOBDポートに専用の診断機器を接続し、電子制御システムにエラーチェックを行うことから始まります。この診断機器は、車両のECUに接続され、エラーコード(DTC)が発生していないかを確認します。これにより、車両の異常や故障箇所を自動的に検出することができます。
次に、各装置の状態を詳細に確認します。エンジン、排気ガス処理装置、電子制御ブレーキシステムなど、重要な装置が正常に機能しているかを検査します。もし異常が発見された場合は、整備士が原因を特定し、必要に応じて修理や調整を行います。この段階で不具合が解消されることで、最終判定において問題なく合格できる可能性が高まります。
最終的に、OBD車検の基準を満たしているかどうかの判断が行われ、合格か不合格かが決定されます。合格した場合は、車両が安全に運転できる状態であることが保証されますが、不合格の場合は必要な整備を実施してから再検査を受けることになります。このように、OBD車検は段階的に車両の安全性と機能性を確認するプロセスであり、ドライバーにとっても安心できる検査システムです。
OBD車検の合否基準と特定DTCの重要性
OBD車検の合否基準は、特定のDTC(診断トラブルコード)が発生しているかどうかに基づいています。DTCは、車両の電子制御システム内で異常が発生した際に自動的に生成されるエラーコードであり、車両に潜む問題を明示する重要な情報です。DTCにはさまざまな種類があり、それぞれのコードは異なる問題を示しています。
特定DTCが検出された場合、車両は不合格となり、適切な修理や整備が必要です。例えば、排ガス基準を超える異常が検出された場合やブレーキシステムに不具合が見つかった場合は、修理が完了するまで安全な運転が保証されません。この合否基準により、車両の安全性や環境性能が確保され、ドライバーと社会全体にとっての安心感が提供されるのです。
また、この基準は単に合否を判断するだけでなく、車両の健全性を維持するための指針としても機能します。特定DTCが検出された場合は、整備工場で適切な対応を行い、車両が安全な状態であることを確保することが求められます。OBD車検の合否基準は、こうした安全性と環境保全に対する確固たる取り組みを反映しており、ドライバーが信頼できる車両を所有できるよう支援する仕組みとなっています。
OBD車検を受ける際の注意点
注意点1:事前点検の重要性
OBD車検を受ける前には、事前に自己診断機能を使用して車両の状態を確認することが非常に重要です。これは、検査の際に突然不具合が見つかってしまうリスクを軽減し、車検の合格率を高めるための有効な手段です。
OBD車検では、エンジンや排気システム、ブレーキなど、電子制御システムの各部分が正常に機能しているかが細かくチェックされます。そのため、自己診断機能を使って事前にこれらのシステムの状態を把握しておくことで、万が一異常が検出された場合でも、あらかじめ修理や調整を行い、スムーズに検査を通過することができます。
例えば、警告ランプが点灯していないか、エラーメッセージが表示されていないかを確認することは重要です。もしエラーメッセージが表示された場合、早急に修理工場で診断を受け、必要な整備を行うことが推奨されます。これにより、検査当日に不合格となるリスクを減らし、結果的に余計な時間や費用を節約することができます。
事前点検を行うことで、OBD車検をスムーズに受ける準備が整うため、ドライバーにとっても安心して車検に臨むことが可能です。特に、電子制御システムに詳しくない場合でも、自己診断機能を活用することで、基本的な状態を確認できるため、事前点検をぜひ行っておくことが重要です。
注意点2:特定のDTCコードに関する留意点
OBD車検では、DTC(診断トラブルコード)と呼ばれるエラーコードが検出された場合、合否に直接影響を与えることがあります。このDTCコードにはさまざまな種類があり、それぞれのコードが異なる故障や不具合を示しています。特に、車両の安全性や環境基準に重大な影響を与えるDTCが検出された場合、修理や整備が必要となります。
DTCコードの中には、エンジンの異常、排気ガスの基準違反、ブレーキの不具合など、重要な問題を示すものがあり、これらはOBD車検において厳しくチェックされる項目です。そのため、車検前には、特定のDTCコードが表示されていないかを確認し、もし表示されている場合には適切な対処を行うことが不可欠です。
たとえば、排気ガス関連のDTCが検出された場合、そのままでは環境基準に適合しない可能性が高く、不合格となるリスクが高まります。このような場合、事前に排気ガス処理装置のチェックや必要な修理を行い、問題を解消しておくことが重要です。DTCコードの確認を怠ると、再検査が必要となり、時間や費用が余分にかかる結果となるため、検査前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。
DTCコードへの対応は、車両の安全性と環境保護に直結する重要な要素であり、OBD車検をスムーズに通過するためには欠かせません。ドライバー自身が意識的に確認を行うことで、車両の健全性を保ち、安全で快適な運転環境を維持することが可能となります。
まとめ – OBD車検を理解し安全なドライビングを目指そう
2024年10月から開始されるOBD車検は、車両の安全性と環境性能を向上させるために新たに導入された検査制度です。この制度は、従来の目視検査や手動による点検に加え、OBDシステムを活用した自己診断機能を通じて、電子制御システムの不具合を迅速に発見できるという利点があります。
ドライバーにとって、OBD車検を受けることで安全性を保つだけでなく、環境への負担を減らすことも期待されます。特に、事前に自己診断機能を使用して車両の状態を確認し、必要に応じて整備を行うことで、車検をスムーズに通過することができ、安心して車を使用することが可能です。
OBD車検の導入によって、より多くの車両が安全基準と環境基準を満たすようになり、ドライバーだけでなく社会全体にとってもメリットがあります。この制度を積極的に受け入れることで、より安全で快適なカーライフが実現し、長期的には車両の寿命を延ばし、費用を節約することにもつながります。
今後もOBD車検の普及により、ドライバーが安心して運転できる環境が整備されると同時に、交通事故の減少や環境負荷の軽減にも貢献することが期待されます。OBD車検を正しく理解し、安全なドライビングを目指していきましょう。
今回もお読みいただきありがとうございました。

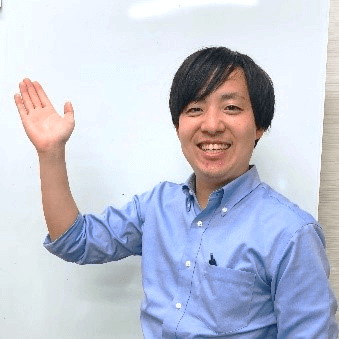
- 出身地
- 埼玉県所沢市
- 担当部署
- リテール営業
- 略 歴
- 2019年にオートアベニューへ転職入社。
「お客様に寄り添う」をモットーに、快適なカーライフの提供に邁進中。新車、中古車、車検などの整備についての最新情報を発信!お客様からの「ありがとう。」を糧に毎日を全力で駆け抜けています!

- 出身地
- 東京都西東京市
- 役 職
- 株式会社オートアベニュー 代表取締役社長
- 略 歴
-
1995年~1996年 オートアベニューでアルバイトをする
1997年~2002年 夫の仕事の関係で5年間オーストラリアへ
2002年4月~ 帰国後 株式会社オートアベニュー入社
2005年 株式会社オートアベニュー 専務取締役 就任
2008年 株式会社オートアベニュー 代表取締役社長 就任 今に至る
車業界歴約30年。現在100年に一度の変革期と言われている車業界、EV化・自動運転・空飛ぶ車などに加え、車検法などの各種法律関係で多くの法改正が行われています。
今まで学んだ多くの事や車業界界隈の様々な事をわかりやすく、皆様にお伝えいたします。